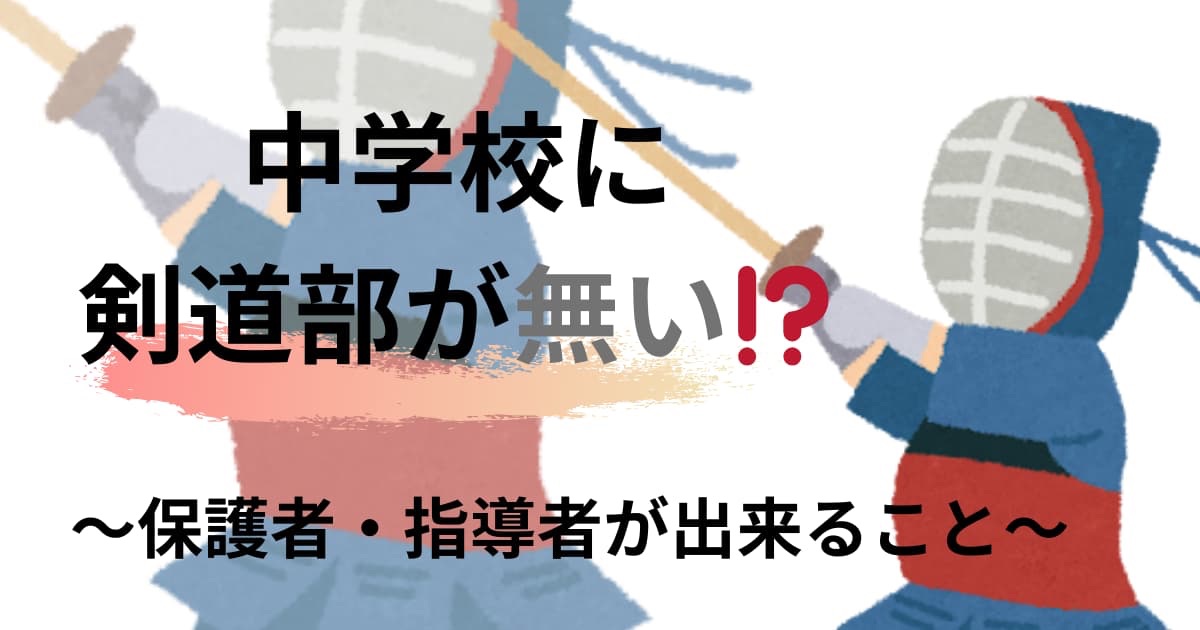剣道ノート第3回目の話題は、『中学校に剣道部がない場合、剣道を続けたい子供に保護者や指導者が出来る事』について考えてみたいと思います。
『剣道ノート』とは?
剣道の稽古・大会・イベントなど、剣道に関わる中での反省点や気付いたことなどを、不定期で雑談的な内容で振り返りをしていくコーナーです。
今までの剣道ノートの内容については、下のリンクから確認することが出来ます。
 すごいちゃん
すごいちゃん良かったら見てくださいね♪
- 小学生で少年剣道を始めて、中学校に行っても剣道を続けたい!でも通う予定の公立中学校には剣道部がない(既に廃部・休部)
- どうにかして、どんな方法でもいいので中学生になってからも、子どもに剣道を続けさせてあげたい
と思って、この記事を見てくださった保護者・指導者の皆さん!!
まさに我が子も同じような状況で、中学校入学前から保護者として、指導者の1人として動いてきました。
子どもが中学校に入学前に関係各所にどのようなタイミングで、どのように働きかけをしたかなど、少しでも参考になればと思います。
ケース1: 文化部に入部しながら中体連に参加して剣道を続ける場合


文化部(吹奏楽部や美術部)であれば、中体連に参加することが出来ます。
卒業式が終わり中学校に入学するまでの間に、保護者から中学校に連絡してもらいました。
中学校では文化部に入りたいと思っているが、小学校から続けた剣道を続けたいと思っているので、中体連の試合に参加したい。
と言った旨の内容です。
このケースの場合は、文化部の先生が中体連の臨時の顧問の先生になって頂けました。
総体・新人戦は現地集合・現地解散が基本です。
文化部の部活をしながら、稽古は夜の少年剣道の時間に小学生と一緒に行っていました。
ケース2: 文化部には所属せず、外部扱いで中体連のみ中学校名で試合に参加する場合


文化部には所属せず、中体連の大会のみ顧問をつけてもらい、試合に出場した場合。
ケース1と違うのは、あくまで部活ではなく社会体育の一環として放課後中学校の武道場を借りて指導者主導で稽古を行いました。
よく聞く『部活動指導員』とはまた別で、あくまでクラブチームのような立ち位置です。
8月後半〜9月頃、市議会議員Aに中学校の剣道部を復活出来ないかと相談したのがはじまり。
市議会議員A・指導者・保護者で、どうしていきたいのか、いくつかのパターンを提示しながら話し合いを行いました。
市議会議員Aに仲介して頂き、中学校の校長・教頭との話し合い。市議会議員Aにも同席して頂きました。
- 剣道部の復部は出来ないけれど、中体連の大会で顧問をつけてもらう
- 部活ではないが特例として社会体育扱いで、学校運営の時間帯(放課後)に武道場を開放して稽古をしても良い
- 校長が変わっても、今回の話し合いの内容は引き継いでもらう(反故・ほごしない)
など出来る限り細かく話し合いをしました。
小学校卒業式後〜中学校入学までの間に、念のためケース1同様に保護者から中学校に連絡してもらいました。
今回の場合は部の掛け持ちではなく、剣道専用で顧問の先生をつけて頂きました。
もちろん中体連の大会は、現地集合・現地解散です。
保護者・指導者・中学校との話し合いの前に押さえておきたいポイント


少しでも早く、子ども達の中学校での剣道ライフの道筋をつけてあげたいと焦るところもあります。
…が、ちょっと待って!
保護者・指導者・中学校と3者が話し合いする前に、頭に入れておいて欲しいことがあります。
剣道部の復部は難しい可能性大!そうなった時の代替案はある?
学校の先生方の働き方改革もあり、昨今一度廃部になった部活の復部はとても難しいものがあります。
『剣道部を部活として復活させることは難しい状況です』と言われた時に、すぐ代替案を出すことは出来ますか?
中学校と話し合いをする前に、保護者同士や指導者も交えての話し合いの場を作り、それぞれの足並みを揃えるのが良いと思います。
中学校との話し合いで市議会議員などを間に挟んだ方が良い理由
私達は当たり前のように、市議会議員を間に挟んでの話し合いを進めてきました。
中学校とのアポ取りなど、細々したことは全て議員さんがしてくれました。
これは近隣の中学校での実際にあった話なのですが…
指導者と中学校の校長とで話し合いをしました。その場ではお互いに納得して大筋が決まったそうです。
が実際に動き始めようとした矢先、後日校長が『そんなことは言っていない』と話し合いの内容の一部を反故(ほご)にされたということでした。
市議会議員など第三者を間に挟むことで、話し合いで決まったことを反故(ほご)されるのを防ぐ事が出来ます。
また、『校長が変わっても今回の話し合った内容は引き継いで欲しい(反故しないでね?)』と念押ししておくのもいいかもしれません。
団体戦が組める人数(5人以上)を長期に渡り少年剣道から送り出せるなら剣道部復活の可能性もあり
『剣道部の復部は難しい』と言われましたが、長期に渡り団体戦が組めるくらいの人数を少年剣道から送り出すことが出来れば、復部は可能とも言われました。
長期と言うのは、目先の2〜3年ではなく最低でも10年以上は…というニュアンスでしょう。
10年以上も少年剣道から中学校に送り出せるくらいなら、そもそも廃部(休部)にはなってないんだよなー。
田舎の過疎化・少子化が進んだ地域には、どうあがいても無理な話です。
近隣地域で剣道部の部員数が少なくなってきているなら、拠点校にして団体戦に参加することも可能
剣道は、2つ以上の中学校がしかるべき手続きを踏むことで、『拠点校』という名前で団体戦に参加することが出来ます。
拠点になる中学校の顧問の先生によれば、手続きには保護者の同意と各中学校の校長印・中学校を管轄する教育長印が必要とのこと。
保護者の見えないところで顧問の先生の手間ばかりかかる感じで、熱心な先生でないとやってくれないのでは?という印象を受けました。
拠点校にするメリットは、人数不足で個人戦しか出られなかった子が、人数が集まることで団体戦にも出られるようになること。
デメリットは、拠点となる中学校以外の中学校の名前が消えてしまうこと。
(拠点A中・B中の場合→拠点A中のみの表記になる)
放課後指導の場合、少年剣道の指導者がどこまでサポート出来るかがカギ
子どもが中学校に上がっても剣道をさせたい!となった時に、我々保護者が求めるゴールはどこなのでしょうか?
- 部活としては無理でも、中学校の名前で中体連に参加出来ればOK?(稽古は古巣の少年剣道で)
- 中学校の名前で中体連に参加するのはもちろんのこと、部活のように放課後に剣道をさせてあげたい!
など色々と落とし所があると思います。
例えば、部活のように放課後の時間帯に剣道となると、どうしても少年剣道の指導者を巻き込まざるを得なくなりますよね。
部活動の地域移行と言われて久しいですが、私達が住む市では、指導者に対してはあくまでボランティア扱いで市からお金が出ることはありません。
そして何より部活動の時間は平日の夕方や土日の午前中。
バリバリの現役世代の若い指導者は、時間的に融通がつきにくいため、剣道以外で周りを見渡しても定年退職された方が放課後指導しているのがほとんどです。
私も保護者でありながら、段位は低いですが剣道をしている身として、サポートメンバーの一員で放課後指導に動いています。
が…全て参加すると結構なハードスケジュール。


放課後指導は、指導者がどこまでサポート出来るかにかかっていると思います。
私の知っている範囲では、子どもの保護者に剣道の経験者が多く、子どものために!と仕事が休みの日に交代で放課後剣道を教えに行っているパターンが1番多いです。
我が子が中学校在学中の時はそれで良いけれど、卒業したら…?
綱渡りの状態が今後も続きそうです。
保護者がどこまで子どもの剣道のために時間を取れるか
話題は変わりますが、保護者の方に質問です。
お子さんが中学生になって、子どもの剣道のためにどれだけ時間を使うことが出来ますか?(時間を取る事が出来ますか?)
中学校に剣道部がない場合は特に、保護者がどれだけ子どもの剣道をサポートが出来るかによって、子どもの剣道の上達具合が変わってくると感じます。
まとめ
今回は入学予定の中学校に剣道部が無い場合、それでも剣道を続けたい我が子に親として出来ることを実体験を交えながら記事にしました。
紹介したケース以外にも、お子さんが中学校に行っても剣道を続けられる道はたくさんあると思います。
ぜひ諦めずに色々な可能性を模索してみてください。